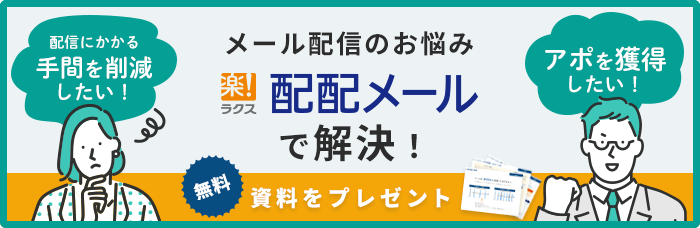【調査結果】対応済み企業の割合は?Gmailガイドライン変更の影響を調査しました!
- メールマーケティング
- 調査データ
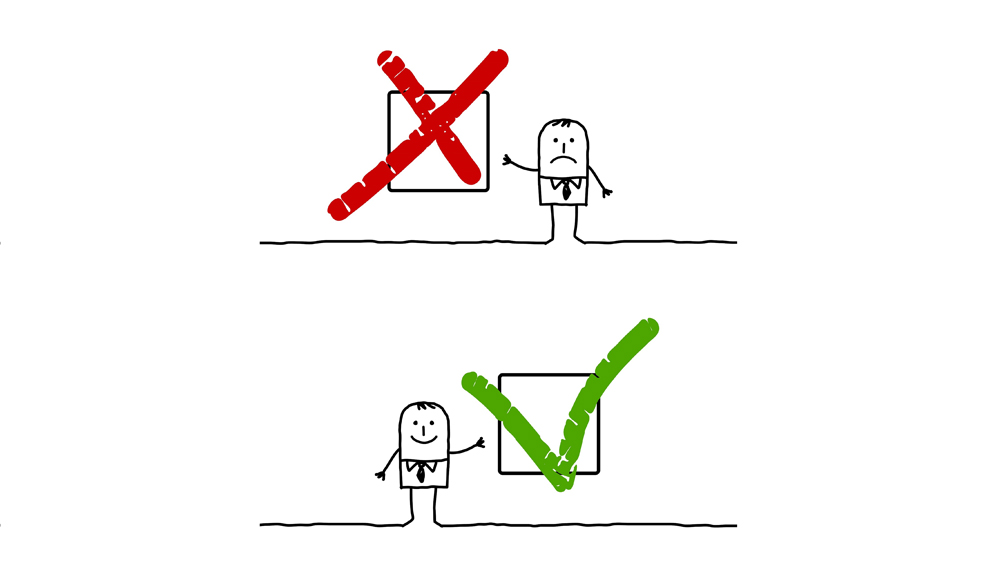
目次
メールに関する法律について紹介している本コラム。第3回目は、「特定電子メール法」(正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)を守りながら、メルマガを運用していくための2つの重要なポイントについて解説します。
>>メールマーケティングの最新情報をお届け! メルラボ / 配配メールのメルマガに登録する
メルマガ担当者になると「オプトイン(opt-in)」「オプトアウト(opt-out)」という用語を目にする機会が増えることでしょう。そこでまず、両者の言葉の整理から始めてみましょう。
メールを受信する人が、広告・宣伝メールの送信が行われることを認識し、「同意」を得ることを指します。そのための条件としては、「一般的な人々が理解できるような形で、広告・宣伝メール送信が行われることがわかるような説明」と、「それに賛成する意思表示があったことを証明できる記録」が必要です。
一度「同意」しても、そのメールを受け取りたくない場合は自由に受信拒否し、その後の送信を禁じることを指します。その際は、簡便にオプトアウトができる方法がメールに記載されていることが奨励されています。
特定電子メール法では、2008年(平成20年)の法改正により「オプトイン方式」を導入しました。その部分を引用してみましょう。
■第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二~四(略)
(特定電子メール法 第一章 第三条)
つまり、メルマガを送る対象者にはオプトインが必要、ということ。
なお、WEB上の記入フォームなどにその同意の有無を確認できる項目を設置する際は、下記のようなことが推奨事項として挙げられます。
・わかりにくい表示(極端に小さな文字・目立たない色・膨大なスクロールを必要とする場所に記載するなど)は避ける
・同意の通知の相手が誰なのかを具体的に表示する
・誤って同意しないために、配信希望欄をデフォルトオフの状態にする
(デフォルトオンの場合は目立つように注意事項を記載する)
・配信の頻度・容量が多い場合はその旨を記載
また、受信者が「同意した」時期や方法などを示す記録などは保存しておく必要があり、その期間は配信停止の日から1か月間が経過するまでと義務付けられています。
とはいえ「では、名刺をもらった人に対してメルマガで育成を行いたいのだけれど、それは違法?適法?」と考えるBtoBメルマガ担当者もいることでしょう。そこで次に、オプトイン方式の「例外」についてご紹介します。
あらかじめ同意してもらわなければメールが送れない「オプトイン方式」ですが、結論から述べますと、「メールアドレスが記載された名刺」をもらった人に対しては、オプトインの必要なくメルマガ送付が行えます。
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(総務省、消費者庁、財団法人日本データ通信協会 2009年)』によると、下記のケースがオプトインの「例外」として、同意なしに広告宣伝メール送信ができるとしています(一部改編)。
・名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合※1
・取引関係にある者に送信する場合※1
・自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合
― 同意の確認をするための電子メール
― 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
― フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの
・自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合※2
※1 送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。
※2 自己の電子メールアドレスの公表と併せて、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。
メルマガ担当者としては、「メールを送れる人」「送れない人」の違いを知り、正しく運用することが不可欠です。そのためにも、オプトイン・オプトアウト方式を理解するとともに、法改正などにも注意を払っておく必要があるでしょう。最後に本記事の参考資料をご紹介しますので、詳細までお読みいただくことをおすすめします。
参考資料
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」
次回は、「特定電子メール法」に抵触しないメルマガ運用のポイントの2回目として「表示義務」について紹介したいと思います。
関連記事:【メルマガ担当者必読講座!メールに関する法律の基礎知識<第4回>】メルマガの「表示義務」とは?~「特定電子メール法」に抵触しないメルマガ運用のポイント(2)~
関連記事:知らないと法令違反?!メルマガ担当なら必ず理解しておきたい「特定電子メール法」について